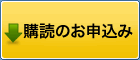こんなハガキが届いた。
「久し振りに出刃包丁でタラと格闘。ヌルヌルでなかなかやっかいでしたが、大きなタラコが入っておりました。昆布〆、思いのほか美味。もう1匹は骨付きぶつ切りで炊いてみました。何だか懐かしい味がしました。干したボウダラが頻繁に食卓に上ったのはいつの頃でしたか。今は大そうな高級品でびっくりです。タラコは塩水に漬け、明太子もどきにしようと目論み中。出来は後日報告いたします。ベーコンとタラとじゃが芋で洋食系もなかなかいけます。冬の味覚、ごちそう様でした」
今号の釣り欄に書いたサクラマス釣りツアーで、狙いのマスは見事坊主を食らい、いわゆる外道、目的じゃないのに釣れちゃったスケソウダラを社員と幾人かの知人にもらっていただいた。そのお礼のハガキである。こちらとしては、「どうだ、うまいだろう」とは威張れない贈り物であるにもかかわらず、こんな丁寧な、差し上げた方が恐縮してしまうような文面。還暦まで、そろそろ秒読み段階、体力・気力の衰えも自覚させられる歳である。絵ハガキの裏に、書き慣れた小さな文字でしたためられた礼状を読みながら、あぁ、こんなふうに、人の気持ちを素直に受け止めて、ふんわりとお返しできる、そんな生き方を意識しなくちゃいかんなぁ、と柄にもなく思った。枕は、ここまで。
「新聞って、すごい」と改めて感動している。朝日新聞の夕刊一面に、月曜日から金曜日まで連載している「ニッポン 人・脈・記」で一月八日からスタートした「魂の中小企業」を読んでの感想だ。全国各地で踏ん張っている中小企業の経営者とその会社に焦点を当て、さらに人脈をたどるという特集記事。そのさわりを。
その三回目(一月十三日付)、「従業員の誇り 私が守る」の見出しで、二人の経営者の生き方が紹介されている。群馬のバネメーカー「中里スプリング製作所」の二代目、中里良一(56)社長は、「大嫌いな取引先は、こちらから切り捨てる」のだそうだ。従業員は二十四人。年に何回か頑張った社員を社長の裁量で表彰する。表彰された社員は、縁を切りたい取引先を「いばる」「嫌みだ」の理由で、申請できる。社長が自分でチェックし、申請が妥当だと判断したら、取引をやめる。これまで何社もの大口取引先をそうやって切ってきたのだという。「下請けとしてお得意様に尽くします。でも、『下請けの分際で』とうちを見下し、従業員の心を傷つける権利はない」と言い切る社長は、取引先を一社切ると、新規を十社開拓するというノルマを自分に課した。どうしたら楽しい会社をつくれるのか、全国各地を講演して歩き、その取引先は千二百七十七社。徳島、高知、鹿児島で開拓すれば、全国制覇なのだという。
もう一人は、「いばるな大企業」を公言し、元ヤンキーや元左官屋などの従業員を試験も面接もなしで先着順で採用しながら、高い技術力でほかに真似のできない超精密な部品を開発し続けている愛知県豊橋市の精密部品メーカー「樹研工業」の松浦元男社長(73)。彼の言葉。「人員削減に追い込まれないように、会社の中身を充実させてきた。規模を追ってきた大企業とは違います」。年末来報道されている、売れ行き不振を理由に派遣社員をいとも簡単に切ってしまう大企業のやり方と、この違いは、どうだ。
第二回(一月九日)には、旭川出身の経営者も登場している。東京で精密加工の会社を経営する金森茂さん(66)。この号の見出しは「下請けをなめんなよ」。貧しい農家に生まれ、グレて少年鑑別所に入った経験を持つ金森社長の来歴と、取引先の大手企業を相手に闘った武勇伝、そしてエレキの神様、寺内タケシとの邂逅などが簡潔な文体で語られている。
北海道、特に旭川地域は、「道新さん」が圧倒的なシェアを誇っているのだが、こんな記事を読まされると、全国紙の企画力と情報収集力、取材力はさすがだと思い知らされる。そして思う。このまちにも、こうした哲学をしっかりと持った、「魂の経営者」が幾人もいるはずだ、と。私たちのアンテナが小さく、そして足を使っていないから、出会えていないんだ…。先の見えない不況感に覆われた時代だからこそ、私たち地元の小さな新聞の仕事が必要とされる、また、必要とされなければならない。ようやく、続いた新年会が終わりつつある一月半ばにして、〇九年の目標のようなものが見えた、気がする、のであります。