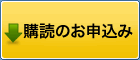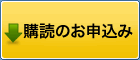この職種に就いて、今年夏で二十五年になる。三十五歳まで、十指に余る職を転々とした。還暦と呼ばれる歳になって、なお、オレはこの仕事に向いていないかも知れない、と時々思う。二十代の前半から八年ほど勤めた野菜の仲卸時代の夢を見ることがある。オレ、やっぱり八百屋が性に合っていたのかも知れない、と本気で考えたりする。職業とは、そういうものだと私は思っている。第一義は飯を食うために、なのだと。好き嫌いは、第六義か第七義か、それくらいのものなのだと。
弊社のような零細新聞社でも、社員を募集するとかなりの高学歴の方が面接に来る。多分、「新聞社」という単語が持つイメージのようなものが、そうした方の職業選択アンテナに触れるのだろう。だが、社の玄関に入って来る様子を見ただけで、お引取り願うかどうかの判断が可能な方も少なくない。
私たちの国は、戦後、どこかの時点で教育というものの概念の規定を間違ってしまったのではないか。
思い返せば、団塊の世代の最後尾にあたる私が小学校、中学校、高校へと進む時代、今のように職場体験のカリキュラムなどなかった。職業の貴賎に関するお説教を学校で聞いたこともない。だが、労働の何たるかも知らない子どもの目に映る、農家や鍛冶屋、大工、畳や寿司の職人といった、いわばモノをつくる人に対する社会的地位は、かなり高かったと思う。五十年前、鍛冶屋のおじさんが赤く焼けた鉄の棒から瞬く間に鍬や鎌を作り出す、手品のような仕事を飽かず眺めていたものだ。
(工藤 稔)
(全文は本紙または電子版でご覧ください。)
●電子版の購読は新聞オンライン.COMへ