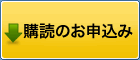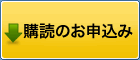十五丁目商店街の小さなすし屋が静かに店を閉じた。仕事上の知り合いと顔を合わせずに、軽く酔いたいときにフラリと立ち寄れる店だった。
帯広生まれ。札幌で修行し、旭川のすし店で働いた後、店主が自分の店を持ったのは昭和三十七年(一九六二年)、二十三歳のとき。同郷で同い年の奥さんのお腹には長男がいた。六条十七丁目のオール商店街、前の経営者が残した借金も、電気代や水道代も店名も、全て引き継いでの開店だった。七十五歳になる夫婦は「何も知らない若造だったから」と顔を見合わせて笑う。
昭和四十三年(一九六八年)、鮮魚店の勧めで、現在の店に移って四十五年になる。店の二階に住み、すしを握って一粒種の長男を大学にやった。閉店の理由は店主の足の具合が悪くなったこと。「値段は十年以上そのまま。この人、いいものを使うから、もうからないの」と奥さん。鮮魚店に待ってもらっていた仕入れの残金は、息子が黙って清算してくれた。「五十一年商売してきて、残せたのは息子だけだったな」と店主は言う。
あっちの名店もこっちの名だたるホテルも、偽装やまがい物の山だ。料理を出す側の倫理の欠如と、食う側の舌や味覚のレベル、高級店には無縁の者が斜めから眺めれば「お相子じゃないの」と揶揄したくもなる。
誠実に一流のネタを選び、それでも価格は庶民でも手が出せるよう努め、ニコニコと黙々とすしを握り続けた職人夫婦が、一線を退いた後、余裕のある老後が送れる世の中であってほしいと願う。どうも政治は、その逆の方向に向かって日々、速度を上げているように思えてならない。年金の支給年齢は上がり続け、支給額はさらに下がる。格差社会は無限に広がり、まちに大量のホームレスが出現する予感…。
(工藤 稔)
(全文は本紙または電子版でご覧ください。)
●電子版の購読は新聞オンライン.COMへ