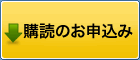――第五十六回北海道新聞文学賞の受賞、おめでとうございます。久しぶりの旭川の印象は。
――第五十六回北海道新聞文学賞の受賞、おめでとうございます。久しぶりの旭川の印象は。
二〇一八年に知床へ行きましたが、旭川は通過しただけでした。その前は二〇一二年、母が亡くなって釧路での葬儀の後、バスで釧路から旭川まで来ました。バスの座席は皆、進行方向を向いていますので誰とも顔を合わさないで済むと思ったことを覚えています。
今回、新しくなった旭川駅の裏手で、迎えに来てくれた弟と待ち合わせました。駅舎はすごく整備され、きれいになっていて、遠くに山が見えて、忠別川が流れて……。私は中学・高校と東光に住んでいて、よく自分の家から忠別川まで散歩をしました。懐かしい川です。
九歳か十歳くらいのときに母の再婚で、旭川へ移ってきました。それから大学まで旭川で過ごしましたが、十代の感じやすい時期のことは、とくによく覚えています。最初に住んだのは三条二十四丁目で、それから東光へ引っ越しました。その時代のことも、今回の受賞短編「オニ」に少し混ぜ込んでいます。
旭川の前に住んでいた釧路は、寒いけれど雪はあまり降りません。今回の旭川滞在中、一日だけ雪が降り、本当に故郷に帰ったという気持ちでした。毛糸の手袋の上に落ちた雪の一粒の結晶は、私が子どもながらも、この世で美しいと思った最初のものです。子ども時代の思い出の多くは雪とつながっています。ストーブが好きで、アイルランドの自宅に薪ストーブを置いているのも、故郷を偲んでのことでしょう。
――「オニ」を執筆した動機の一つに、詩集『雨の合間』(二〇一二年)が第五十五回小熊秀雄賞を受賞したことがあったそうですね。
外国に住んでいますし、文学について日本語で話す友人もいません。私が何もしなくても、誰からも何も言われませんから、創作活動はすべて、自分一人のことです。ただ、『雨の合間』を出版したのが十一月で、小熊賞の締切は翌年の一月でしたから、小熊賞への応募は間に合いそうだなという感じは、なんとなくありました。
小熊賞選考委員の堀川真さんには「誠実な観察」、アーサー・ビナードさんには「シンプルだから強い」と選評されて、非常にうれしく思いました。観察すること、シンプルでなければいけないということ。この二つは、私の文章作法上の美意識であり、私が信じてきたことです。それが初めて理解されたという実感をもちました。まれな言葉や、気取った言葉の使い方を私は意識的に避けてきました。そういうことはしないで表現はできると思ってきました。ですからお二人の選評は、「オニ」を書くうえで支えになりました。
さらに小熊との関わりで、驚くことがありました。私は絵を観るのがとても好きで、「オニ」は、上村松園の「焔」という日本画に着想を得ています。源氏物語の登場人物である六条御息所がモチーフで、嫉妬のために鬼のような形相をしている女性が描かれています。
一方、小熊秀雄の息子が「焔」という名であることは前から知っていました。そして、焔さんの二十年という短い命を思うとき、そんな激しい名前を小熊が付けたから、その焔に息子さんは焼かれてしまったでしょうと、小熊を恨むような気持も抱いていました。つね子夫人にとっては、小熊が死んで、息子も奪われました。焔さんが生きていたなら、夫人の生涯も全く違ったものになったことだろうと、思わないではいられませんでした。
そしてこの旭川滞在中に、驚く話を聞きました。小熊が上村松園論を書いていることは知っていましたが、焔さんの名は上村松園の「焔」からとられたのだと、文学資料館の沓澤章俊さんが調べて、おしえてくださったのです。その同じ絵が私の小説のきっかけとなったという偶然に、言葉を失うくらい驚きました。
――東高の大先輩である佐藤喜一さんが、五十五年前に第一回北海道新聞文学賞を受賞しているという偶然もあります。
佐藤喜一先生は私の恩師です。佐藤先生の道新文学賞受賞作が『小熊秀雄論考』で、小熊の名を冠した賞を私がいただいて。その小熊賞受賞が私を激励して、できあがった短編が道新文学賞を受賞したわけですから。誰かが書いたシナリオという感じですね。
佐藤先生は高校一年の時に国語の担当だっただけですが、何か、ほかの先生とは雰囲気が違いました。自分の世界に生きている方、という感じがしました。
先生が褒めた他の生徒の俳句を今でも憶えているくらいです。「愛別の 朝日に赤い ナナカマド」という句で、「『あ』が三つあるのがいい」と佐藤先生が評されました。「あ」でも「い」でもよいのですが、言葉の最初が同じ音であると、声にしたときに気持ちのいいものなんだということが、十代の私の発見でした。いま七十三歳になって振り返れば、そのころから言葉というものを、私は絶えず考えていたのでしょう。