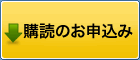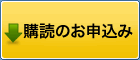大新聞の、しかも社説に難癖をつけるようで、いささか臆するのだが、書く。九月二十八日の早朝、読者でもある知人から電話があった。「天塩川の流域住民って、そんなに毎度毎度、洪水の被害を受けているのかい」。
彼はその日付けの北海道新聞の社説を読んで電話をよこしたと言う。北海道開発局が本体工事が凍結されていたサンルダム(上川管内下川町)の建設継続を決めたことを受けて「議論は尽くされたのか」との見出しの社説である。電話の主は「建設予定の天塩川流域はたびたび洪水被害を受けてきた。地元が治水対策を求めるのは当然である」の文言に怒っている。
きっとこの社説を書かれた方は、天塩川とはあまり縁がない、もしかすると、天塩川やサンル川を実際に、つぶさに見ていない、その水に触れていないのかも知れない。読んで直感的にそう感じた。
私は天塩川とは縁が深い。祖父の代にはJR宗谷線の敷設工事に携わり、今も難所として知られる音威子府―中川間の現場で仕事をした。現在は駅舎もないが、亡父は神路という小さな村落で生まれた。その時代の田舎のほとんどがそうであったように、川沿いのわずかな土地を耕し、自給自足のような暮らしだった。春には必ず、天塩川があふれる。その頃の人たちは「水がつく」と言った。洪水はいわば年中行事だった。
思い出話をもう少し続ける。小学一年の秋から二年生の春まで、今は砂澤ビッキ記念館・エコミュージアムおさしまセンターになっている筬島小学校に通った。一・二・三年生、四・五・六年生が一つの教室で学ぶ複々式の学校だった。天塩川の水はまだ清涼で、川底に僕達はカラス貝と呼んでいたが、カワシンジュ貝がびっしりと敷き詰めたように“立って”口を開けていた。柳の枝で川底を適当に突けば、カラス貝がいくらでも“釣れた”。夏は泳いだ。ヤマベが釣れた。川は暮らしの中にあった。
社説にある「たびたび洪水被害を受けてきた」のは、大雑把に言えば、少し前の時代、つまり昭和二十年代から四十年代頃までの話である。最近では、開発局が営々と続けて来てくれた堤防整備や排水機場の設置などの洪水対策のお陰で、洪水被害は滅多に発生しない。
(工藤 稔)
(全文は本紙または電子版でご覧ください。)
●電子版の購読は新聞オンライン.COMへ