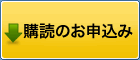ボールペンの替え芯を買いに、文房具屋さんに行った。四年ほど前、知人からいただいたもので、キャップの部分を回すと黒と赤の二色の芯が入れ替わる。仕事に、私用に、毎日使っているお気に入りのペン。芯を取り替えるのは、これで五回目にもなる。健忘症と言ってもいいほど、何でもなくし、我ながら「一生のうちで目覚めている時間の半分を捜し物に費やしているのではないか」と嘆息する日々を送る私にしては、奇跡的な長持ちである。
替え芯は、赤も黒も一本八十四円。女性の店員が、小さな引き出しから数種類の芯を出してきて、私のペンに合う一本を選んでくれる。予備も含めて四本、しめて二百五十二円のお買物なのだが、なんとなく気分が良い。「ありがとう」の言葉が、自然に口をついて出る。この安価な商品の、多種多様な在庫を用意して、いつ来るか分からない客を待っている。使い捨てが当たり前、せせこましい経済競争の中で暮らしているけれど、モノを買ったり、売ったりするって、本来、こういうことなんだろうなぁ、と一人ごちながら落ち葉が舞う道を会社に戻った。
知人からわけていただいた大根を干した。霜にあたらぬよう、夜は家の中に取り込み、空を見上げて雨の予感があれば筵(むしろ)をかけたりして、一週間。かつての庶民の秋の習わしを、その気分も併せて少しばかり楽しんだ。で、今朝、十五丁目の魚屋さんのミガキニシン、自然食品の店「北海道大地」で買い込んだ野菜と麹を材料に、ニシン漬を漬けた。キャベツと大根を切り、ニンジン、生姜を刻みながら、世の中が便利になるに従って、私たちが失っていったものの大きさが、ふと頭をよぎった。
NHK第一「地球ラジオ」の「世界まるごと質問箱」の中で、トルコの小さな町に住む日本人女性のリポートがあった。暖房は石炭。ストーブの上に鍋や窯を乗せて、パンを焼いたり、煮込み料理を作るのだという。雪の季節を前に、越冬用の保存食を手作りしている彼の地の人々の生活が脳裏に映った。そして、たかだか四十年前の暮らしを思った。私たちも石炭や薪で暖を取り、その熱を使って母や祖母が料理を作っていたっけ、と。
いま、居間にデンと据えられたFF式の石油ストーブは、油屋さんが来て石油を入れてくれるし、勝手に温度を調節してくれたりして、石炭小屋から手を真っ黒にして石炭を運んで来る面倒も、煙突掃除も必要なし、あくも出ず、まことに便利ではある。けれど、その上に鍋を乗せて煮豆を炊いたり、干しいもやスルメをあぶることはできない。ストーブは、ただ、暖房の用に使うだけの道具に成り下がった。私たちは、便利さと、触ってもやけどをしない安全を手に入れる代償として、暖房はストーブ、料理はレンジ、お湯はボイラーと、何とも非効率、高コストの生活をするよう仕向けられ、そのエネルギー浪費生活に、まことに従順にどっぷりと浸かってしまった。
ノスタルジーで暮らしや経済は成り立たないことは自明だし、今さら石炭ストーブを家庭に持ち込もうなんて、一般的には妄想に近いのも承知している。その上で、私たちは身近な周りの生活に、疑問を持ちつつ暮らさなければいけないのだろう。北極の氷が融けてホッキョクグマが近い将来、絶滅の危機に瀕するとか、南の島で海の水位が上がって生活できなくなっている、なんてニュースには、「あらら、かわいそうね。大変ね」と危機感を少々感じるフリをするけれど、日々の生活は何も変わらぬ、変えられぬ、である。
「美しい国」も「美しい星」も、この国が推し進める規制緩和、市場原理主義、競争格差社会への助長の動きの中では、夢、幻の戯言でしかない。国レベルの経済を安定的に発展させながら、地球温暖化への対策を進めて、温室効果ガスを減らすなんて土台無理な話よ、と毒づきつつ、さて、家庭レベルで画期的に温室効果ガスを減らす妙案はないものかと頭をひねりながら、ニシン漬けの樽に重石を乗せた。